IRMMW-THz 2025 (50th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves) は、赤外線・ミリ波・テラヘルツ波分野における世界最大規模かつ最も歴史のある国際会議であり、2025年に記念すべき第50回がフィンランドのアールト大学にて開催された。本会議は1974年に創設されて以来、基礎物理から応用技術まで幅広い領域が包括的に取り扱われてきた。
今年の会議には700件を超えるアブストラクトが投稿され、約650件が採択された。参加者の地域分布としては、中国からの投稿が最も多く、次いでドイツ、日本と続き、合計で35か国から研究者が集結した。発表形式は口頭発表が261件、ポスター発表が319件で構成され、会場の至るところで活発な議論が展開された。
また、50周年の記念大会として、分野を牽引してきた著名研究者による「ヒストリカルセッション」が設けられ、会議の歩みとともに今後の展望が語られた。これにより、赤外・ミリ波・テラヘルツ波研究の歴史的背景と国際的ネットワークの重要性が再確認された。
プログラムは4つの主要トピック [1] Material Science、[2] Source and Detectors、[3] Components、[4] System and Applicationで構成された。最も多くの割合を占めたのは、[4]であり、医療や生物応用を中心に全体の34.4%を占めた。サブトピックでは、メタマテリアル・メタサーフェスに最も多くの投稿があり、実用的なセンシング応用に関する注目が高まっていることが示唆された。


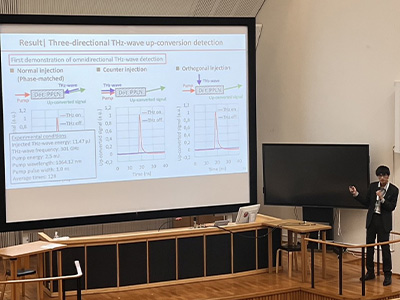
私は、「Coherent THz-wave Phase Detection By Nonlinear Optical Interferometer With PPLN BW-TPO Process」という題目で口頭発表を行った。
将来のインフラシステムを支えるCFRPやGFRPの非破壊検査を目的とし、テラヘルツ波の高感度(最低検出感度10 aJ)かつ高コヒーレントな位相検出(可視度0.89)の実証を報告した。具体的には、斜周期分極反転ニオブ酸リチウム(PPLN)結晶におけるバックワードテラヘルツ波パラメトリック発振(BW-TPO)を用いて、近赤外光とテラヘルツ波を変換する非線形光学干渉計を構築して実現した。この結果は、テラヘルツ量子検出に向けた重要なマイルストーンである。また、全方位フォノンポラリトン結合を介した、位相整合条件に縛られないテラヘルツ波のコヒーレント検出を初めて報告した。検出構成にかかわらずテラヘルツ波の位相を近赤外変換光から検出できることを実証した。 検出構成の自由度を格段に向上させる提案であり、質疑応答では、この位相検出に関して興味を示していただき、結果の評価方法や実験条件などの質問をいただいた。発表後には、関連分野の研究者と、原理について深く議論を行い、本研究の拡張性や今後の研究課題について気づきを得る機会となった。

本会議の初日に行われた学生ワークショップを始め、各セッション(プレナリー、オーラル、ポスター)はもちろんのこと、ランチやディナーも含め、国内外の幅広い研究者と交流することができた。特に、初日の学生ワークショップで知り合った国内外の学生と、お互いの発表を聴講し、学生間で遠慮なく質疑応答を重ねることで研究に対する深い理解が得られた。また、ランチやディナーでは、知り合った学生や若手の研究者から、関連分野の著名な先生方へと挨拶する機会をいただいた。私は、博士後期課程から研究テーマを変更したため、本会議がテラヘルツ波分野の初めての国外の国際会議への参加であり、同分野の著名な研究者や若手研究者と交流する非常に重要な機会となった。
国外の研究者、特に若手の方々と交流して特に印象的だったのが、自身の研究を積極的にアピールしていた点である。彼らは、自分の研究の意義や社会的インパクトを明確に伝えることで、聴衆の関心を引きつけるプレゼンテーション技術にも優れていた。こうした姿勢は、日本の学会ではあまり見られない傾向であり、文化的な違いを強く感じた。このような積極的なアピールは、研究者としての認知度向上や国際共同研究の機会獲得、さらには研究資金の獲得にもつながっていく可能性がある。今回の経験を通じて、研究成果を効果的に伝える力の重要性を再認識するとともに、今後の研究活動においても、より積極的な情報発信を心がけていきたいと考える。
本会議への参加にあたり、貴財団から多大なご支援をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。
