
International Conference on Materials and Intelligent Manufacturing(ICMIM)は、材料及び製作技術に関する研究テーマを取り扱う国際会議である。2017年に第1回ICMIMがシンガポールで開催されて以来、札幌や仁川などで会議が開催されてきた。第7回ICMIMで取り上げられるトピックとして、“Materials Processing Technology and Materials Sciense” と “Design and Manufacturing Systems” が紹介されていた。“Materials Processing Technology and Materials Sciense” の中に “Optical / Electrical / Magnetic Materials” や “Thin Films”、“Micro / Nano Materials” など、自分の研究に極めて近い内容が紹介されていたので研究成果を投稿し、採択していただいた。
第7回ICMIMは、シンガポールのBuona Vista 駅から徒歩10分ほどの場所に位置する、Nanyang Technological University のone-northキャンパスで開催された。発表当日は、Keynote SpeechやInvited Speech を終えたのちに、我々学生を含む口頭発表によるセッションが二つの部屋で同時に開催された。会議全体で37件の研究成果の発表が行われた。
“Strip-loaded magneto-optic waveguides for optical isolator employing nonreciprocal radiation-mode conversion”という題目で研究発表を行った。光通信システムでは、光源に用いられる半導体レーザの発振安定化のため、非相反素子である光アイソレータは必要不可欠である。近赤外領域では、光アイソレータを構成するとき、磁気光学効果の大きな磁性ガーネットが用いられる。現在実用化されている光アイソレータはファラデー回転を利用したバルク型素子であるが、集積化には適していない。将来の光集積回路実現のため、導波路構造により光アイソレータを製作することが強く望まれている。非相反移相効果を利用した光アイソレータは、TM(Transverse Magnetic)モードのみで動作するために位相整合条件を必要とせず、磁界の制御が容易であるという利点を有する。非相反移相効果は、光の伝搬方向に対して垂直かつ膜面内に磁化が配向された磁気光学導波路内を伝搬するTMモードの伝搬定数が、順方向と逆方向で異なることにより得られる。非相反移相効果を応用することで、非相反な導波モード-放射モード変換を利用した光アイソレータが実現できる。これまでリブ構造の磁気光学導波路で非相反放射モード変換型光アイソレータを設計し、光アイソレータとして動作する導波路のリブ幅とリブ高さの条件を明らかにした。
今回、ストリップ装荷型導波路で構成される非相反放射モード変換型光アイソレータを提案し、磁気光学導波路が光アイソレータとして動作する条件を調べた。適切な屈折率の媒質をストリップとして採用することで、磁気光学導波路が非相反放射モード変換型光アイソレータとして動作する導波路パラメータの条件が、リブ導波路を用いた素子の場合と比較して、著しく緩和されることが分かった。
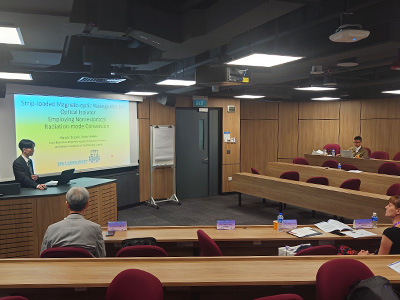
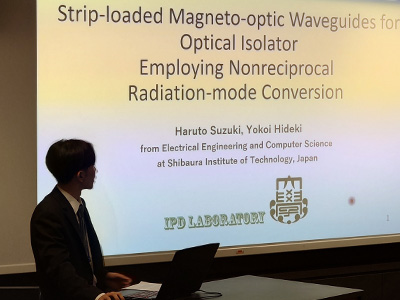

第7回ICMIMに参加し、研究成果を口頭で発表した。
光アイソレータの設計に関して、定められた時間(13分)以内に発表を終えることができた。会議はセッションに分かれており、自分のグループは光材料とデバイスに焦点を当てたトピックで、7人で構成されていた。光通信領域を専門としない参加者が多かったということもあり、研究内容に関する質問はされなかった。雰囲気としては、資料に記載のあったフォーマルというより、カジュアルなスタイルの印象を受けた。そのような会議の中で、異分野を専門とする方々の独自のアプローチや知見などに触れることができ、自らの研究に対する姿勢や視野の向上に繋がった。5日間の滞在で国際会議での学術的な交流に加え、地域の人々との交流の機会があり、英語を始めとするコミュニケーションについての学びを得ることができた。これを機に、多様な人物とかかわりを重要視し、多角的な視点を持つ人物となる礎としたい。
最後に、この場をお借りして一般財団法人丸文財団に多大なるご支援を賜りましたこと深く感謝申し上げます。
