
Replaying Japanは日本のゲーム文化・教育ゲーム・産業に関する国際学術会議である。2025年はオーストラリアのメルボルンにあるRMIT Universityで開催された。メルボルンは世界中から人々が集まる都市であり、街並みからも多様な文化の融合を感じられた。また、メルボルン中心地にはトラムが走っており(一部区間は無料)、宿泊施設から会場までの移動に便利であった。
今年のテーマはHomebrew: hobbyist games, hacks and (other) homegrown activitiesであり、11のセッションで発表が行われた。セッション名は、Modding、usingAI、Design、Physical Worlds、Histories、Exhibitions & Museums、Textual Practices、Fandoms & Communities、Gender Expression、Transculturalismと多様であり、テーマに関する広い分野が集まった。発表形態には、口頭発表、デモ発表、ポスター発表、ライトニングトークがあった。
次回は2026年に日本の立命館大学で開催予定である。
競技かるたは日本で親しまれている伝統的な対戦型カードゲームであるが、日本語や百人一首の和歌の知識や暗記を前提としており、参入の敷居が高く、また楽しめる人が限られていた。本研究では、より多様な人が競技かるたを楽しめるようにするため、和歌の読み上げを単純音の回数に置き換え、その数に対応するトランプ札を取る形に再設計した。これにより読まれた札を特定し、検索し、触るというプレイヤの行動や「決まり字」を巡る駆け引きは保持しつつ、言語性と必要な和歌の知識、暗記を排除する。また読み上げ情報を、視覚情報および・聴覚情報としてより公平な形で提示することが可能になった。 質疑応答では、単純音の再生の間隔の違いが与える影響、単純音以外での音の再生方法について、および提案手法からオリジナルの競技かるたにどう誘導するか、などを討論した。

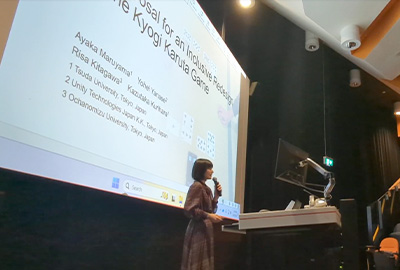

発表後、複数の参加者から感想・助言を得た。セッション内外で活発な議論が行われ、ゲームデザインに関する知見も得られた。さらに、海外の参加者と実際に提案ゲームで競技かるたを楽しむことができ、提案ゲームによって言語・文化背景に依存せず競技かるたを楽しめることを実証できた。また、他の研究者の発表もゲームとSDGs、ジェンダー平等など多岐にわたっており、当該研究領域の最前線を学ぶことができた。
本国際会議への参加にあたり多大なご支援をいただいた貴財団に感謝申し上げます。
