本会はIEEE(米国電気電子学会)の後援のもとで開催されており、太陽エネルギーの研究、開発、技術応用に関わる研究者、技術者、産業界の専門家が世界中から集まる歴史のある国際会議である。本年はアメリカ国外で開催となったため、現地参加できない者のために対面・オンラインのハイブリッド形式で行われた。5日間の間、一般のセッションに加えて、基調講演やチュートリアルセッションが開催された。また、企業や研究機関の展示ブースも併設されるなど規模も大きい。口頭発表は225件、ポスター発表は336件で、80%が直接会場で、20%がオンラインで行われた。


高度な情報社会の実現に向けて、高い変換効率と汎用性を持つ太陽電池が望まれている。
多接合太陽電池は高い変換効率を持つものの、基板として用いる単結晶ゲルマニウム(Ge)のコストが高い。そこで、ガラスやプラスチックなどの汎用基板上に多結晶Ge膜を合成して、単結晶基板の代用とすることが検討されている。しかし、従来の多結晶膜では高密度の粒界と多数のアクセプタ型欠陥が光励起キャリアを散乱・消滅させるため、基礎的な性能指標である「分光感度(出力電流/照射光強度)」が得られた例すらなかった。特に光吸収に望ましい厚い膜(≥ 500 nm)では、結晶粒径が矮小化する傾向にあり、粒界密度が高くなる。
候補者は、従来の結晶成長技術を改良して、大粒径薄膜(50 nm)の合成とそれを種結晶層としたエピタキシャル成長という二段階の成長を考案した。このようにして、ガラスやプラスチック上において太陽電池応用に望ましい厚い膜(500 nm)でありながら、大きな結晶粒径を持つ多結晶Ge膜を合成した。その結果、粒界密度とアクセプタ欠陥をそれぞれ1/10以下にまで低減させて、光励起キャリアの取り出しに成功した。特に、プラスチックのようなフレキシブル基板において、Geの分光感度の実証は史上初である。候補者はさらに、欠陥を低減させるためのポストアニール処理や水素プラズマ処理、光吸収量を増大させるための厚膜合成(≥ 1 μm)を行うことで、分光感度を約10倍向上させている。
本研究は多接合太陽電池の汎用化と低コスト化に大きく資する成果である。
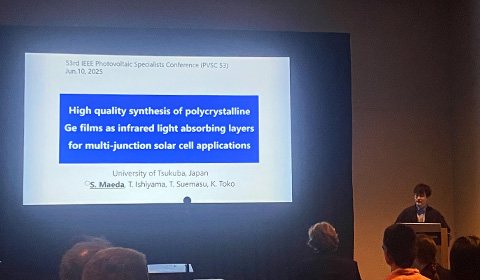
本会議は12のエリアからなり、各分野の最先端の研究発表が行われる。学生は各エリアで専門家に混じって発表を行う。特に口頭発表に関しては、事前に提出されたアブストラクトの中から審査されて数名選ばれるという狭き門である。私は、「Innovative architectures for next generation PV」というエリアでの口頭発表を行なった。その結果、Student awardの最終候補者(上位数名)にも選出された。発表では滞りなく説明することができたうえに、質疑においても活発に議論を交わすことができた。発表の後に、わざわざ声をかけていただくこともあり、そこでお互いの研究について話すことができたのは貴重な経験になった。
自身の発表だけでなく世界中の研究者の発表を見る機会があった。中でも太陽電池のデバイス構造に関する研究は興味深かった。これまで、材料に注目して、いかにより良いデバイス性能を実証するかということを目標にしてきた。しかし、その材料のポテンシャルを最大限に発揮できるようなデバイスの構造があるということを痛感させられた。
以上のように、自身の発表で世界中の研究者と議論できたこと、多くの研究者の発表から自身の研究にフィードバックできたことは、非常に良い機会となった。
今回の有意義な国際会議に参加するための海外渡航に助成いただいた一般財団法人丸文財団に深くお礼申し上げます。
