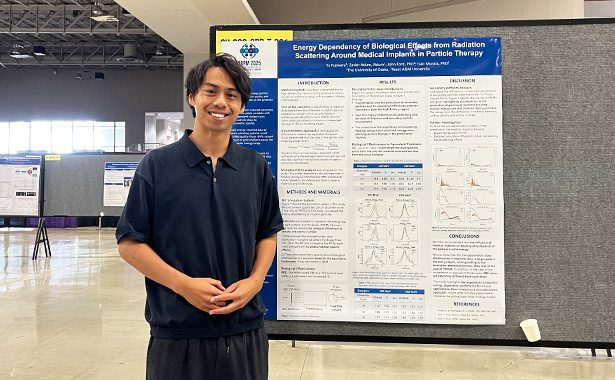本会議は米国の「American Association of Physicists in Medicine(以下,AAPM)」が主催する医学物理学(Medical Physics)に関する年会大会である。具体的には、放射線治療における画像解析技術(CT・MRI等)に関する研究、放射線治療における治療時の生物学的効果を解析する手法に関する研究、そして放射線治療時の治療計画(放射線を照射する角度・強さ・時間など)の最適化に関する研究をはじめとして、主に米国を中心として、これらの医学物理学の知見を学部生にどのように教育するかに関して、各大学の取り組みが報告されていた。
本年度は、これらの研究に関して、アカデミア、インダストリの関係者が集い、5,000件以上の研究成果の発表及び企業展示が行われた。その中で私は、「Energy Dependency of Biological Effects from Radiation Scattering Around Medical Implants in Particle Therapy」というテーマでポスター発表を行った。(詳細は次項に示す)
他方で、本会議の中で医学物理士になるための講座や各分野に関するレビュー講座などが開催されていたほか、キャリア講座も開催され、主に米国でアカデミア・スタートアップなどのキャリアパスをどのように歩むかに関する講演会の開催及び 1 on 1でのメンタリングも行われていた。
私の研究テーマは医療用インプラント(ペースメーカーや歯科インプラント等)を持つ患者に対して放射線治療を実施する場合に、インプラントが周辺組織に及ぼす影響についてシミュレーションを使って解析するというものである。インプラント材料はチタン合金などが用いられることが多く、その密度及び原子番号は通常の人体組織に比べて大きく異なる。したがって、放射線の通り道にインプラント材料がある場合、その散乱・吸収などの相互作用の程度も異なることから、がん細胞に望ましい放射線量が照射できないことや、周辺の通常組織に予期せぬダメージが与えられるリスクが生じる。このような人体組織と異なる材料が存在する場合の線量を評価する手法は一応存在しているものの、放射線と物質の相互作用の不確実性を十分に評価しているとは言えず、各患者に合わせて個別に評価することが必要であると我々の研究グループでは考察していた。
この仮説を実証するため、陽子線治療・重粒子線治療などの粒子線治療を対象として、「マイクロドジメトリ」という概念を用いて、様々な厚さの生物組織等価材料及びインプラント材料(チタンと金)に対して粒子線を照射し、通過後の放射線の挙動をシミュレーションによって解析し、その結果から生物物理モデルを用いて relative biological effectiveness (RBE) と呼ばれる生物学的効果を評価した。そして、現状の評価手法では放射線と物質の相互作用を十分反映しているとは言えないという我々の仮説を実証する結果をシミュレーションレベルで実証した。
本発表では、これらの成果を報告し、今後実験によってこの仮説を裏付けるためにどのような工夫が必要か、そして、実際の治療条件を反映して、更に高精度なシミュレーションを行う手法について議論した。
【コミュニケーション】
本発表を通して、2 で挙げた議論テーマに関して重要な示唆を得ることができ、今後の方向性が明確になった。具体的には、「このソフトウェアのシミュレーション精度が優れている」という話や、実際に人体組織を詳細に模擬してシミュレーションコードに組み込む手法が紹介されていて、そのような方々と交流できたことは非常に良い経験であった。
【国際交流】
本学会を通して、主に米国の学生及び Faculty の方々と交流することができたのは、今後の自身のキャリアにとって非常に大きなステップになったと思う。特に、1on1 のメンタリングでは、初めは何もわからない状態で参加したが、メンターの方から米国で医学物理士になるための具体的な手順をご教示いただき、大変勉強になった。また、担当されていたメンターの方々がはじめは医学物理の専門家 (Ph.D.の専攻) ではなく、「原子力工学」というバックグラウンドを持っている私について、「大きな武器になる」と励ましてくれたことは、今後アカデミアでのキャリアを目指す私にとって大きな励みになるものだった。
【感想】
以上、今回の発表機会を通して、自身の研究の進展及びキャリア開発のために重要なアイデアを多く吸収することができた。普段は原子力工学を専門として放射線治療に関わってきた自分にとって、医学物理の観点から見た「放射線治療」のトレンドを覗くことができたことは、普段味わうことのできない貴重な経験だったと考える。