
PCSI(Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces)は、表面及び界面における物理的・化学的現象の基礎解明並びに応用研究を推進する国際学会である。学会では、物質の成長プロセスや界面現象、新規評価手法の開発が取り上げられ、半導体ヘテロ構造、トポロジカル材料、エネルギー関連材料、二次元材料、高誘電率・強誘電体、酸化物半導体、ニューロモーフィックコンピューティング材料、量子センシング材料、有機及びハイブリッド半導体、磁性材料、光電子分光、並びに点欠陥など、広範な先端分野が議論される。毎年開催される会議は、ワークショップ形式を採用し、参加者間の活発な討論と知見の交換を促進している。今回参加したPCSI-50は、2025年1月19日から23日まで米国ハワイ州カイルア・コナのOutrigger Kona Resort & Spaにて開催された。国際的に著名な研究者や技術者が一堂に会し、最新の成果や今後の展望を共有する重要な学術交流の場となった。
本会議において、私は「Realization of smooth surface and interface in Mist CVD growth of rocksalt structured-MgZnO/MgO MQWs」と題し、ショートプレゼンテーションおよびポスター発表を行った。
岩塩構造の酸化マグネシウム亜鉛(Rocksalt (RS)-structured MgZnO)は、最大7.78 eVという広いバンドギャップを有しており、水銀灯に代わる新たな紫外線殺菌光源として注目されている。当研究グループは、ミスト化学気相堆積法(ミストCVD法)を用いて岩塩構造MgZnOの成膜に成功している。ミストCVD法は、溶液を霧化し、ガスを用いて基板へ前駆体を輸送する成膜技術である。この手法は非真空下で成膜可能なため、一般的な真空を用いる成膜方法に比べて比較的低コストで成膜できるという利点がある。LEDの開発には量子井戸構造の実現が不可欠であるが、これまでミストCVD法による岩塩構造MgZnO系量子井戸の報告はなかった。そこで本研究は、ミストCVD法を用いて岩塩構造MgZnO/MgO多重量子井戸(MQW)の製作を目的とした。
本発表では、実際にミストCVD法を用いて製作した岩塩構造MgZnO/MgO MQWについて報告した。原子間力顕微鏡(AFM)および走査型電子顕微鏡(FE-SEM)によって良好な表面モフォロジーが観察され、さらに走査透過電子顕微鏡(STEM)による断面の観察から、急峻な界面を有する積層構造が形成されていることが確認された。

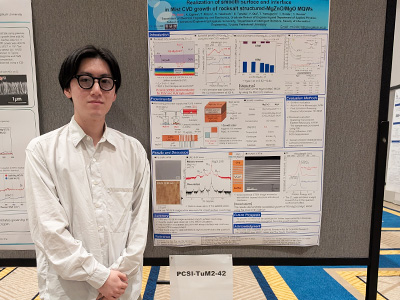

今回の学会は、自身にとって初めての国際学会であり、また、英語での発表および議論も初めてであったが、入念な準備の甲斐もあって、特に問題なく発表を終えることができたと感じた。しかし、発表直後の質疑応答においては、完璧な回答ができず、自分の英語力の低さを痛感した。今後は、専門的な知識の習得に加え、国際的に活躍できる人材として英語でのコミュニケーション能力の向上にも力を入れていく必要があると感じた。
会議外の時間においても、ハワイ島の自然に触れる機会やハワイならではの食事を楽しむ機会があり、有意義な時間を過ごすことができた。特に、ハワイ島は火山の噴火活動によって形成された島であるため、その自然の雄大さを実感することができた。
最後になりますが、本学会に参加するにあたり、貴財団から多大なるご支援を賜り、心より感謝申し上げます。この学会で得た知見や経験を今後の研究に活かし、より一層精進してまいります。
